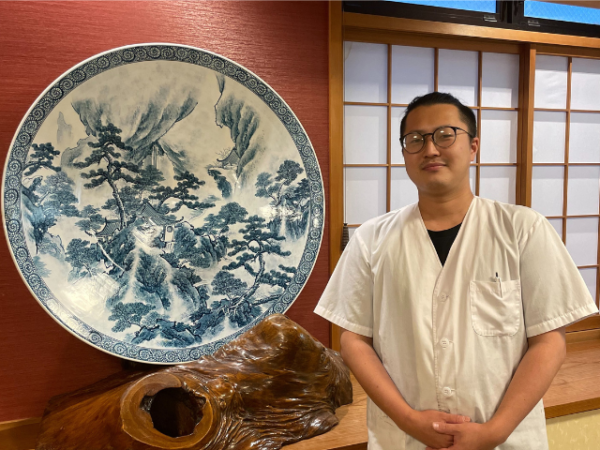
75年続く此花の味を未来へ。“ギブの連鎖”で育てる日本料理の現場|濱寿司
此花区に根差し創業75年。仕出しや宴会対応を軸に2店舗を展開する濱寿司。専務・蓮見大誠が目指すのは、料理人に無理をさせず“ホールもできる板前”を育てる現場づくり。ギブを重ねる濱寿司の姿勢に迫る。
株式会社濱寿司 専務取締役 蓮見大誠(はすみたいせい)
Q:蓮見専務、今日はよろしくお願いします。まず最初に株式会社濱寿司の事業内容から聞かせて頂けますでしょうか?
1949年に曽祖父が地元此花区で創業し、日本料理を中心に提供してまいりました。 現在は、創業場所である此花区に密着し、宴会や法要、忘年会など大人数の集まりにも対応可能な2店舗の運営に加え、仕出し弁当やお寿司の配達も行っております。
Q:ありがとうございます。蓮見さんは、現在30歳の若さで専務取締役としてご活躍されていますが、どのような経緯で経営に携われるようになったのでしょうか?
濱寿司は蓮見家で代を継いできたこともあって、物心ついたときには、僕も継ぐものだと自然に思っていました。なので卒業と同時に調理師免許を取得できる高校に進学したんですよね。そして、卒業後は懐石料理を学ぼうと京都が本社の会社に就職することになるのですが、配属先が東京に。3年間上京することになりました。その後、大阪に戻り2年ほどお寿司の勉強をした後、濱寿司に入社。そして、ガムシャラにやっているうちに経営的なところも担当するようになり、気付いたら専務を任されるようになっていました。

Q:なるほど。蓮見さんは料理一筋だったわけですね!専務を任されるにあたって何か大切にされているお考えなどがあればお聞かせください。
料理人にムチャをさせないような環境づくりを心掛けています。濱寿司には「お客さまファースト」というずっと受け継がれてきた考え方があります。日本料理のお店でありながら「餃子がたべたい」と言われたら、それっぽいものを即席でお作りする。「パスタがたべたい」と言われたら、やっぱりそれも作る。そんな具合でお客さまのご要望に極力、応えてまいりました。そんな姿勢でいたからこそ、お客さまに支持されてきたといっても決して言い過ぎではないんですね。しかし、その裏では、そのご要望をお受けする料理人に負担がかかっていました。それはそうですよね。作ったことのない日本料理以外のものを即席で作るわけですから。ですのでまずは、その辺りの環境改善から取り組んでいます。
Q:具体的にはどのような取り組みを始められたのでしょうか?
まずは定休日を作りました。濱寿司はお店が休みの日でも配達の仕事があるので会社自体はほぼ休まず動いていることになるんですね。ゆえに、休みが取りづらい環境にありました。ですので、まずは休みを作ることからはじめました。そして、今まさに取り組んでいることは、注文のときだけお客さまとの接点を減らすことです。スタッフが席までいって注文をとると、どうしても「これ作れる?」「あれできる?」となってしまいがちなんですね。ですので各席にタブレット端末を設置することにしました。こうすれば、タブレット端末内に表示されているメニューしか頼めないので、結果、料理人の負担を減らすことに繋がります。もちろんお客さまとのコミュニケーションが減ることも懸念されますが、そこは、今後の様子をみながら解決していこうと思っております。

Q:なるほど。タブレット端末の設置は人件費を削減する目的で導入されるケースが多いですが、濱寿司さんでは労働環境を改善するために導入されるんですね。さて、この辺りから読者の方が気になってそうなことを聞いていきますよ!御社に入社すると、まず一番最初に取り組むことはどんなことでしょうか?
3~4ヶ月の研修期間を経て、ホールスタッフ希望か、料理人希望かヒアリングさせていただき、極力、その要望通りのお仕事をしていただきます。その後は、近くにある2店舗間を行き来してホールスタッフが料理を、料理人がホールスタッフをするようになります。なぜそうするかというとホール業務と料理の両方ができてはじめて一人前である、という考え方が濱寿司にはあるからです。やはりお店の運営はホール業務だけができてもダメですし、料理だけができてもダメなんですよね。
Q:確かにそうですよね!中長期的にはいかがでしょうか?
濱寿司では、お節料理を作れるようになることが一人前になれたかどうかの最終テストみたいな位置づけになっています。なぜなら、料理人としてのすべてがそこに現れるからですね。お節料理には焼きもの、揚げもの、炊きものなど、日本料理の代表的な技法が集約されています。そして、それぞれの技法を濱寿司では最低でも1年間かけて身に付けてもらいます。今年は焼きもの、来年は揚げもの、といった具合ですね。そしてホール業務もやりながら一人前になれれば10年もしないうちに独立も目指せます。そうやって、何人もの料理人が今までに暖簾分けしていきました。

Q:創業75年という期間を考えると、今まで何人もの方々が濱寿司で日本料理を学び、卒業されていったかと思います。そんな従業員さんたちにはどんな想いをお持ちですか?
濱寿司を第2の家族だと思ってほしいです。もちろん卒業していった方の中には、料理とは別の道に進んだ人たちもたくさんいます。そんな方々にも家に帰るのと同じように濱寿司に帰ってきてほしいと思っています。なぜなら同じ釜の飯を食べた仲間と再会するとパワーをもらえるからです。僕がそう思うということは、卒業した人たちもきっと何かしらのパワーをもらっているはずなんですよね。そのパワーを活力にかえて頑張ってほしいと思っています。
Q:ありがとうございます。インタビューも終盤ですが、ここで蓮見さんの思う飲食業の素晴らしさをお聞かせください。
料理を通して、お客さまと「ギブ」を与え、返しあえる関係性になれることだと思います。私たち濱寿司は、お客さまにどうやったら喜んでいただけるかを徹底的に考え、それを実行に移してまいりました。それが僕たちのできるギブですね。そして、その対価をお金でいただくわけですが、ここまでは普通のことです。ですが、ここから先ですよね。お金以外のことでもギブを返していただけるんですね。たとえば、美味しいフルーツを「これ食べな!」なんていって頂戴したり、壊れたお店の生簀を無償で修理していただいたり、なんてこともありました。そして、また料理を通してギブをお返ししていく。そんな関係性になれることが、この仕事の醍醐味だと僕は思っています。

Q:ギブの連鎖ですね!最後になりますが、読者の皆さまへメッセージをお願いします。
人は満足すると成長が止まってしまいます。限界を作らず、更なる高みを目指してください。

